非常時持出品の準備
ページID Y1000525 更新日 令和7年3月31日 印刷

「いざ避難!」というときに備えて、非常持出品を用意し、ひとまとめにして、取り出しやすいところに保管しておきましょう。
目の不自由な人は「緊急連絡カード」、耳の不自由な人は筆談ができるように「メモ帳」なども用意しておきましょう。とくに内部障がいのある人は、「かかりつけの医療機関の連絡先」や「常用の医薬品」なども用意しておきましょう。
災害時に身元が確認しやすいように、運転免許証、障がい者手帳、母子手帳などの身分証や緊急連絡カード(緊急連絡先やかかりつけ医療機関などを記入したもの)を携行しましょう。
非常持出品の例を例示しましたので参考にして、自分用の非常持出袋を準備しましょう。
持ち出し品リスト
水
水は3日分用意するといいです。飲料用として1人1日3リットルを目安として9リットル程度。生活用としては1人1日7リットル程度を確保しましょう。一般的な保存期間の目安はペットボトルで1年から3年程度(冷暗所に置いた場合)です。随時保存期間の確認をしましょう。
生活用の水の確保のためにも寝る前にポットややかんに水を入れておく、お風呂の水をためるなど行いましょう。
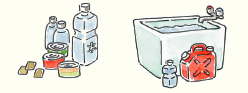
非常用食料
少なくとも3日分は用意しましょう。そのまま食べられるか、簡単な調理で食べられるものが便利です。アルファ米やレトルトのご飯、缶詰、レトルトのおかず、インスタントラーメン、切り餅、チョコレート、氷砂糖、梅干、インスタント味噌汁、チーズ、調味料、など。定期的に期限を確認し、古いものから食べて、いつも新鮮なものを補充するようにしましょう。
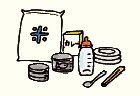
通帳類・証書類・印鑑・現金
預金通帳・健康保険証、免許証など。また、現金は紙幣だけでなく公衆電話用の10円硬貨も用意しましょう。
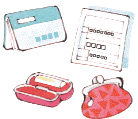
携帯ラジオ
デマに惑わされないよう正確な情報を得るために、小型で軽くFMとAMが両方聞けるものがよいです。予備電池も忘れずに準備しましょう。

懐中電灯・ろうそく
懐中電灯は停電時や夜間に移動する際の必需品です。予備の電池も忘れずに用意すると安心です。
ろうそくは、太くて安定するものを選びましょう。
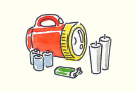
ヘルメット(防災ずきん)
避難途中に屋根瓦や看板などの落下物に当たったり、転倒することもあるためヘルメット(防災ずきん)で頭部を守りましょう。
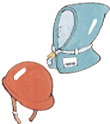
衛生用品・救急薬品
ばんそうこう・ガーゼ・包帯・三角巾・体温計・消毒薬・解熱剤・胃腸薬・かぜ薬・目薬・爪切りなど。
特に、持病のある人は常備薬も忘れずに準備しましょう。
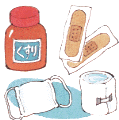
燃料
卓上コンロ、固形燃料や予備のガスボンベは多めに用意しましょう。アウトドア用の携帯コンロも便利です。

マスク
救出救助の時ほこりを防げます。また、避難所などでの感染症予防にも役立ちます。

その他
めがね、入れ歯、上着、下着、靴下、ハンカチ、タオル、ウエットティッシュ、軍手、ラップフィルム、ティッシュペーパー、ビニールシート、なべ(コッヘル)、使い捨てカイロ、雨具、ガムテープ、手ぬぐい、筆記用具(マジックなど)、スコップ、ビニール袋、笛(ホイッスル)など
※ 乳幼児がいる場合…ミルク、ほ乳ビン、おむつ、バスタオル、授乳服、授乳ケープなど
※ 要介護者のいる場合…着替え、おむつ、障がい者手帳、常備薬など

避難するにあたって注意することは?
避難が必要なときは、身体の不自由な人やその家族へ声をかけ協力しましょう。
避難する前に火気を確かめ、完全に消します。電気のブレーカーも忘れずに切りましょう。
非常持ち出し品など、持ち物は必要最小限にしましょう。
底の厚い、履きなれた靴を履きましょう。(長靴は水が入ると動きづらくなります。)
行動しやすい長袖、長ズボンを着用しましょう。
軍手を着用しましょう。
避難することになったら、集団で協力し合って最寄りの避難所へ避難しましょう。
避難は原則徒歩で、自動車などの使用はできるだけ控えましょう。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災課 防災グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
