自主防災組織とは?
ページID Y1000547 更新日 令和7年9月18日 印刷
自主防災組織って何?
みなさんは災害時の「自助」・「公助」・「共助」という言葉を聞いたことありますか?
「公助というのは、公共の防災機関、例えば消防、警察、自衛隊による災害時の救助活動などをさします。
災害時、この「公助」が当然市民のために全力で行われなければなりません。しかし、この公助だけでは大きな災害にはほとんど無力です。また、大規模災害が発生した場合、「自分の身は自分で守ろう(自助)」という、一人だけの力にも限界があります。
そこで、「自分たちの住んでいる地域は自分達で守る」、地域の人々のまとまった力、これを「共助=自主防災組織」 といいます。この「まとまった力」は、むろん、ただ待っているだけでできるものではなく、地域の人々の意思といきごみと協力で作られるものです。
自主防災組織はなぜ必要なんだろう?
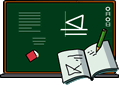
災害発生時、被害を最小限にとどめるよう、防災機関は総力をあげて防災活動に取り組みますが、災害によって道路の寸断、建物などの倒壊、津波による災害、断水や電力供給の停止など、多種多様で同時に数カ所発生する恐れもあります。関係機関は、様々な障がいで到達に時間がかかる、あるいは到達できないという最悪のケースもありえます。
そこで、災害が発生したとき、防災機関の機動力が到達して活動するまで間、逃げ惑うのではなく、被害の拡大を防ぎ命を守るために力を合わせて活動することのほうが重要で本来のあるべき姿ではないだろうかと誰もが考えるはずです。しかし、救助活動や消火活動を各個人で行おうとしても、個人の力には限界があり、かえって危険な場合もあります。そこでは個々がばらばらの活動をするよりも組織として集約された力の活動の方がはるかに有効です。
自主防災組織の活動について
自主防災組織の目的
自主防災組織の目的は、災害発生時の初期活動に有ります。消防などの防災機関が現場に到着して活動を開始するまでの間、初期活動を地域で組織的に行えば被害は最小限に抑えることができます。
- 被害の拡大を防ぐ
- 付近の人たちを避難誘導する
- 混乱をさける
平常時の活動
・防災知識の普及
防災カルテ、防災地図の作成、講習会、防災映画などの上映会の開催
・地域の災害危険の把握
地域の危険箇所や防災上の問題点を確認・改善
・防災訓練
初期消火訓練、避難誘導訓練、救出・救護訓練など
・防災資機材・設備器具の点検
資機材の動作確認など
・防災資機材の備蓄
災害発生時の活動
・救出・救護
応急手当や心肺蘇生法などを習得しておきましょう。
・出火防止・初期消火
出火から3分以内のまだ天井に火が回っていない状態が限度です。
・避難誘導
タンカやリヤカーなども備えておきましょう
・情報の収集および伝達
「いつ・どこで・だれが・どうして・どのように」の要領で情報を収集し、伝達する。災害時に市へ報告していただきたい情報は、
(1)人的被害(死者、行方不明者、重軽傷者など)
(2)住家・建物被害(全半壊、焼失、浸水など)
(3)その他(公共設備、道路、橋、水路、河川などの状態など)
避難行動要支援者対策に取り組もう
避難行動要支援者とは
お年寄り、乳幼児、障がい者、外国人などの災害発生時に弱い立場に立たざるを得ない人々が多数存在します。この方たちへの支援や協力には、隣近所の人たち、地域の人たちの支援体制が必要不可欠です。
自主防災組織で取り組む避難行動要支援者対策
- 弱い人たちの立場になっての防災環境の点検
- 障がい者を交えての防災訓練
- 地域での協力・支援体制を具体的に決める。
- 地域住民の意識啓発
自主防災組織に参加しませんか
市内には、60を超える自主防災組織があります。
いざというときにお互いが助け合えるように、積極的に地域の活動に参加しましょう。
お住まいの自主防災組織が分からない場合は、市役所防災課までお問い合わせください。
自主防災組織への助成制度について
自主防災組織の結成および補助金交付申請まで
ステップ1 組織づくり
まずは、自治会(町内会)の会議(役員会・総会など)で自主防災組織の必要性を議題にし、規約や役員などを決め、総会などで自主防災組織結成案を討議し、可決します。
ステップ2 市への結成報告
自主防災組織結成届出書に次の書類を添えて、市役所防災課に提出して下さい。
- 自主防災組織規約
- 自主防災組織役員名簿
- 自主防災組織防災計画書
ステップ3 結成補助金の申請
自主防災組織の結成届出後1年以内に防災訓練を実施した場合、1組織につき1回のみ補助します。
補助金交付申請書に次の書類を添え、事業着手前に市役所防災課に提出して下さい。
- 事業計画書
- 収支予算書
補助金額
基本額7万円に(50円×世帯数)を加算します。ただし、10万円を限度とします。
参考様式
補助金概要 ※令和7年度の「資機材などの整備に必要な経費に対する補助金」受付は予算上限到達により終了しました。
活動補助金
結成補助金の交付を受けた自主防災組織に対して、次年度から防災訓練参加人員数に応じて1組織につき年度1回を限度として補助します。
補助金額
防災訓練参加人員数別の補助額
-
100人未満 1万円
-
100人から199人 2万円
-
200人から299人 3万円
-
300人以上 4万円
参考様式
-
交付申請書類【活動費】 (Word 21.0KB)

-
実績報告書類【共通】 (Word 21.7KB)

-
(記入例)交付申請書類【活動費】 (PDF 109.8KB)

-
(記入例)実績報告書類【活動費】 (PDF 100.8KB)

資機材などの整備に必要な経費に対する補助金 ※令和7年度の受付は予算上限到達により終了しました。
次のような資機材を購入した経費に対して補助します。ただし、備蓄食料などの消耗品類は対象としません。
- 防災倉庫(簡易収納庫)
自主防災組織の備蓄、資機材倉庫 - 初動消火資機材
可搬式小型動力ポンプ、可搬式散水装置、大型消火器、スタンドパイプ、組立型水槽、ホースボックス、その他初期消火活動に必要な資機材 - 救助用資機材
携帯用無線通信機、ハンドマイク、発電機、投光器、チェーンソー、エンジンカッター、可搬式ウインチ、チェーンブロック、ジャッキ、担架、梯子、救命ロープ、油圧式救助器具、その他救助活動に必要な資機材 - 救護用資機材
ろ水器、救急医療セット、防水シート、揚水機、毛布、簡易ベッド、簡易トイレ、炊飯装置、リヤカー、防災井戸、マスク、体温計、手袋、消毒液その他救護活動に必要な資機材 - 訓練用資機材
人命救助訓練用人形、訓練用消火器具、その他訓練に必要な資機材 - 防災に関する研修
講演などにおける講師謝礼(手土産代を除く。)※講演などにおける講師は、大学および分野の専門講師とするため、事前に市役所防災課に相談してください。
補助金額
事業費の85%以内
ただし、50万円を限度とします。また、算出された交付額に、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
参考様式
-
交付申請書類【防災資機材費・研修費】 (Word 22.1KB)

-
実績報告書類【共通】 (Word 21.7KB)

-
(記入例)交付申請書類【防災資機材費・研修費】 (PDF 174.3KB)

-
(記入例)実績報告書類【防災資機材費・研修費】 (PDF 126.6KB)

管理運営規定および管理状況台帳の作成について
補助金を活用して購入した防災資機材などについては、適切な維持管理、運用のための管理運営規定および管理状況台帳を整備してください。
参考様式
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災課 防災グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
